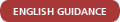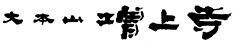目に見える大きな生き物も
目に見えない小さな生き物も
近くに生息している生き物も
遠くに生息している生き物も
すでに生れ出た生き物も
これから生まれてくる生き物も
命あるものはみな幸せでいてほしい
ブッダ『スッタニパータ』第147偈より
鳥たちが鳴き分ける鳴き声には意味があり、鳥たちは「鳥語」を操り会話をしている。最近、若き研究者によって動物言語学という研究分野が開拓され、研究の成果が世界的に注目されているそうです。長期間にわたって森に滞在し、シジュウカラを観察しながら鳴き声を収集、幾通りもの鳴き声と行動を分析し、地道な検証実験を重ねた結果、「ヘビだ!」「タカだ!」といったいくつもの単語を使い分けるばかりか、「警戒して集まれ」など文章を組み立てているというのです。
鳥が鳥語を操っている。ファンタジーを覆す衝撃的な研究に、「よほど鳥が好きじゃないとそんなことできやしない、どれだけ鳥のことが好きなのだろう」とその研究者に興味が湧きました。調べてみると、今年になって出版された鈴木俊貴著『僕には鳥の言葉がわかる』はすでにベストセラー。「鳥好き」を通り越して鳥の世界に同化している研究者の姿に魅了されながら、「動物たちの会話を理解し、かれらの世界を知った時、僕たちの世界はもっと豊かで素晴らしいものに変わるはずだ」という結語に大きくうなずきました。
ブッダ(お釈迦様)当時のインドでは、出家者は屋外の自然の中で修行に励むことも多かったはずです。ブッダはそうした仏道修行中の心得として、「命あるものはみな幸せでいてほしい」という思いで臨めと、弟子たちに諭します。仏典に「仏心とは大慈悲これなり」ということばがあります。ブッダはじめ修行者たちは様々な生き物を観察し、それぞれの世界に同化しようとしていたのでしょうか。生き物の言葉を理解するブッダがおられたとしてもファンタジーとはいえないような気がしてきました。
教務部長 袖山榮輝