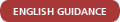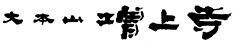釈尊(お釈迦様)はさとりを開いた後、はたして修行をする必要があったのか。
もう何十年も前のことですが、大学で仏教学を学んでいたある日の講義、教授が私たち学生にそう問いかけてきました。さとりを開く過程であるならともかく、さとりを開いた後のことなどまったく関心がなかった私にとって、思いもよらぬ視点でした。
釈尊の事跡を伝える古代インドの文献を丹念に読み込むことで知られた教授は、釈尊がいつ何時どこにおられたか、そうした視点から釈尊の行動を読み解く研究者でした。その日、教授はある文献を紹介しながら、真夜中の森の中で釈尊が一人、ある種の瞑想にふけっていたと解説しました。そして、その瞑想は煩悩を打ち消すための修行であるとおっしゃったのです。煩悩を打ち消してさとりを開いた釈尊は、その後も、自身に再び煩悩が湧き起こらないように修行し続けていた、というのが教授の主張する釈尊像でした。
仏教においては「身体を動かす」「言葉を発する」「思いをめぐらす」といった自分自身の「行い」を重要視します。何か行動を起こせば、そのことがある種の影響力となってしばしの間残り、自分自身にはたらきかけてくる。善きにつれ悪しきにつれ「行い」の影響力が生じては消える中、釈尊は悪行から遠ざかり弛むことなく修行することで、さとりの境地を保ち続けたのです。
2月15日は釈尊の命日。弟子たちに向けた最後のおことばを、現代人向けに表現し直してみました。ちなみに釈尊の最後のおことばと、法然上人の御遺訓とされる『一枚起請文』の一節「只一向に念仏すべし」は重なっているように思います。
教務部長 袖山榮輝